Q&A よくある質問 (第二期FSS2022-2025年度)
<問い合わせ先><概要><応募資格><応募方法><応募型><受講準備><経費・保険>
<講座の受講と修了><研究テーマ><その他>
<問い合わせ先>
Q01-01.
問い合わせ先はどちらですか?
A01-01.
本事業の募集・その他一般的な問い合わせについては、下記(FSS事務室)までお願いいたします。
静岡大学 FSS事務室 TEL:054-238-4848 FAX:054-238-4828
![]()
問合せフォーム
<概要>
Q02-01.
「未来の科学者養成スクール(FSS)」はどこが運営しているのですか?
A02-01.
「未来の科学者養成スクール(FSS)」は、国立大学法人静岡大学(https://www.shizuoka.ac.jp/)が運営しています。
このプロジェクトは、科学技術振興機構(JST)「グローバルサイエンスキャンパス」の委託事業です。
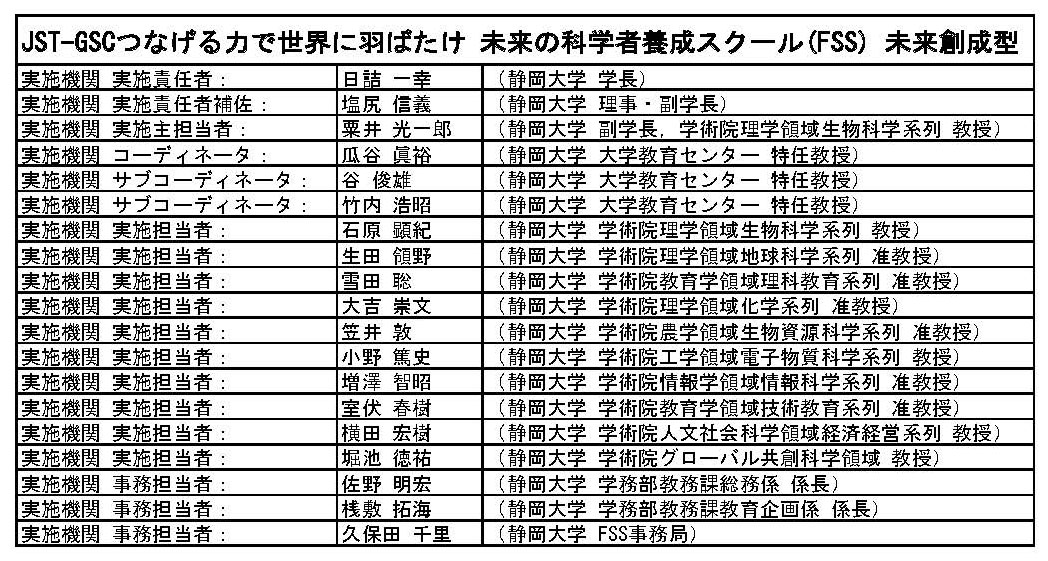
Q02-02.
「グローバルサイエンスキャンパス」ってなんですか?
A02-02.
「グローバルサイエンスキャンパス」(https://www.jst.go.jp/cpse/gsc/)は、科学技術振興機構(JST)の事業のひとつで、大学が、将来グローバルに活躍しうる傑出した科学技術人材を育成することを目的として、地域で卓越した意欲・能力を有する高校生等を募集・選抜し、国際的な活動を含む高度で体系的な、理数教育プログラムの開発・実施等を行うことを支援します。教育プログラムは、個に応じた才能育成の施策や、受講生の多様性に応じた育成プランが組み込まれたものであることが求められます。
Q02-03.
FSSでは、どのようなことを行いますか?
A02-03.
FSSには「基礎力養成コース(第1段階)」「研究力養成コース(第2段階)」「研究力発展コース(第3段階)」の3つの段階があります。
「基礎力養成コース」では、最先端の研究内容の講義や研究者として必要なスキルを身につける講義を受け、その講義に対するレポートを作成して理解を深めます。
「研究力養成コース」以降の段階では、静岡大学の研究者の指導を受けながら研究をします。併行して、研究の社会実装をテーマにしたワークショップを行います。
Q02-04.
FSSの教育プログラムには、どんな特徴がありますか︖
A02-04.
静岡大学の理念である「自由啓発・未来創成」を具現化した教育プログラムです。
この教育プログラムには、次のような特徴があります。
①大学教員の講義を受け、自由な雰囲気で自主的に学び合うことができます。
②異なる地域の異なる学校から、科学・技術について多様な視点を持った高校生が集い、交流ができます。
③高校生の発想を尊重した研究を行い、良い成果が出た時は科学コンクールへの発表や学会発表に挑戦できます。
④研究の社会実装をテーマにしたワークショップで行う討論やプレゼンテーションを通し、未来創成を担う科学者、技術者に必要な国際性、アントレプレナーシップなどの素養・資質を養うことができます。
Q02-05.
FSSでは国際交流の機会がありますか?
A02-05.
①「研究力養成コース(第2段階)」では、「海外大学生との交流-英語活用能力・プレゼンテーション能力の向上-」というワークショップを行います。ここでは、自分の住む地域の課題を考察し、科学的な解決方法を提案します。このとき、ティーチングアシスタント(TA)として静岡大学に通う外国人留学生が資料作りの討論に加わり、英語で議論をします。また、作成した英語の資料を使い、シンガポール国立大学の大学生の皆さんとリモートで討論します。
②「研究力発展コース(第3段階)」の研究発表会の後、選抜された受講生の代表が海外に派遣されます。2024年(3月)、2025年(3月)には、インドネシアの大学を訪れ、現地の大学生に向け研究発表、討論を行ったり、同国の自然環境や産業について研修を行ったりしました。
Q02-06.
FSSを受講すると、どんな力が身につきますか?
A02-06.
「基礎力養成コース」では科学研究に対する分野横断的な視点の獲得を目指します。また、研究者倫理、科学的な文章を書く力、社会課題などをテーマに討論する力、研究テーマを設定する上での情報収集力など、研究者として必要なスキルを養います。
「研究力養成コース」「研究力発展コース」では、研究を遂行する力、研究成果を外部に発信する力を養います。併行して、英語でコミュニケーションを行う力、研究を社会課題の解決に繋げる発想を体験的に獲得するプログラムがあります。
Q02-07.
FSSを受講すると、何か資格が得られますか?
A02-07.
FSSは資格を目指す活動ではありませんが、以下の項目が活動履歴として所属高校に報告できます。
①「基礎力養成コース(第1段階)」の終了時(1年目12月)、「研究力養成コース(第2段階)」の終了時(2年目6月)、「研究力発展コース(第3段階)」の終了時(2年目の3月)に、各コースの修了要件を満たす受講生には「修了証」を発行します。
②FSSの研究で成果が上がった場合、高校生対象のコンテストへの参加・受賞、学会発表、学術雑誌への論⽂掲載など、具体的な形での活動報告として外部に発信することができます。
Q02-08.
FSSに入ると、大学進学にプラスになりますか?
A02-08.
昨今の大学入試では、FSSのような校外活動への参加歴を重視する傾向にあります。
ただ、その扱いの軽重や評価方法は大学・学部・学科ごとに違います。進学を希望している大学等の募集要項を確認してください。
<応募資格>
Q03-01.
現在、高校2年生ですが、2年目(高校3年)に継続受講できるかどうかわからなくても、応募できますか?
A03-01.
応募資格には「2年目継続受講の確約」は含まれてはいません。高校2年生で入校すると、高校3年の6月に行う研究発表会をもって「研究力養成コース(第2段階)」の修了となります。そこまで活動継続が可能かを、研究力養成コースへの応募時期(高校2年次の9月)の段階で判断してください。
Q03-02.
現在、高3ですが応募できますか?
A03-02.
できません。大学受験など、卒業後の進路の準備に専念してください。
Q03-03.
応募資格のひとつに「月に1回以上、静岡大学静岡キャンパスに通えること。」とありました。部活などの関係で1回も通えない月ができそうなのです(応募時に未確定の⽉間予定あり)が、応募できますか?
A03-03.
応募できます。
ただし、欠席があまりにも多い場合は各課程の修了を認めません。
どちらを優先して参加するかは、自分で判断し、選択して下さい。
Q03-04.
他機関の企画とFSSを⼆重受講してもいいですか
A03-04.
科学技術振興機構(JST)に採択されている「次世代科学技術チャレンジプログラム」「グローバルサイエンスキャンパス」との二重受講はできません。
ただし、他機関と併願することに制約はありませんが、両方に受講が認められた場合はいずれかをキャンセルする必要があります。自分に一番合うと思った企画に応募することをお薦めします。
<応募方法>
Q04-01.
「未来の科学者養成スクール(FSS)」に応募するには、どうしたら良いですか?
A04-01.
応募型に応じて応募書類を作成し、提出してください。「エントリー&方法(https://fss.shizuoka.ac.jp/entry/)」サイトの説明に従って応募書類(志願書,研究内容報告小論文,調査書)を入手し、それぞれの応募型に必要な書類を「書式添付で応募」サイトから提出してください。
Q04-02.
応募型によって、提出する書類は違いますか?
A04-02.
応募型は【A】自己推薦・一般型 【B】自己推薦・自主研究推進型 【C】学校推薦・連携活動型 【D】特別推薦総合型 の4種類があります。提出する書類は以下の通りです。
A型:(本人が作成)志願書
B型:(本人が作成)志願書 研究内容報告小論文
C型:(本人が作成)志願書
(在籍する高校の先生等が作成)調査書をWEB入力する
D型:(本人が作成)志願書
(在籍する高校の先生等が作成)特別調査書をWEB入力する
Q04-03.
申込書の欄が狭くて書ききれないのですが。
A04-03.
各応募書類に示された項目に従って1次選抜を行いますので、枠内・文字数制限内に収め、定められた書式で応募してください。
「エントリー&方法」のサイトで入手できる書式ではない書類のみを提出した場合、例えば過去に作成したレポートのコピーのみが「研究内容報告小論文」の代わりに提出された場合はエントリーを無効とする可能性があります。
Q04-04.
追加資料(例えば自主研究のレポートや受賞歴を示す表彰状の写しなど)の添付は必要ですか?
A04-04.
必要ありません。
また「エントリー&方法」のサイトで入手できる正式な書式ではない書類のみを、正式な書類の代替として提出した場合はエントリーを無効とする可能性があります。
(正式ではない書類の例:過去に作成したレポートのコピー)
Q04-05.
エントリーサイトからオンライン入力・確認後に「送信ボタン」をクリックしましたが、エントリーできているのか心配です。確かめる方法はありますか?
A04-05.
オンラインでのエントリー手続きでは、「送信ボタン」をクリックした直後、入力情報の確認メールを自動的に、エントリー時入力されたご自身のメールアドレス宛に送信します。同時に静岡大学FSS事務局メールアドレスにも送信されます。
また、事務局職員が受付を確認後、再び登録されたメールアドレス宛に確認メールを送信します。発信者は静岡大学FSS事務局です。これは受付番号の連絡とメール環境確認のためです。
Q04-06.
「入力情報の確認メール」あるいは「FSS事務局から確認メール」の受信が確認できない場合は、どうしたら良いですか?
A04-06.
原因として、確認メールが迷惑メールフォルダに自動的に振り分けられている、入力されたメールアドレスが間違っている、携帯端末でメール受信拒否に設定されている、Webシステム上のトラブルなどが考えられます。
エントリーが完了していない場合がありますので、お問合せフォーム (https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1586171401VGJghgOz)あるいは電話(054-238-4848)・Fax(054-238-4828)などで事務局へ連絡いただくようお願いします。
<応募型>
Q05-01.
自主研究の経験がありますが、「B:自己推薦・自主研究推進型」ではなく、「A:自己推薦・⼀般型」にエントリーすることはできますか?
A05-01.
自主研究の経験があっても「A:自己推薦・⼀般型」にエントリーすることはできます。
Q05-02.
科学部で実施しているテーマとは異なるテーマで「A:自己推薦・⼀般型」にエントリーできますか?
A05-02.
高校の科学部などに所属している場合(高校の部活や学科単位で科学に関する活動を行っている場合)でも「A:自己推薦・⼀般型」にエントリーできます。
Q05-03.
私は、研究らしい研究はしていませんが、小学校の頃から理科が得意科目です。総合的な探究の時間でも、先生から高く評価されました。「B:自己推薦・自主研究推進型」で応募して良いでしょうか?
A05-03.
「B:自己推薦・自主研究推進型」は、すでにある程度の自主研究が進められていて、それを発展させたい⼈向けの応募枠です。自宅や学校、科学館などでの自主研究の経験や理科コンクールなどに発表するためのレポート作成の経験がなければ、「A:自己推薦・⼀般型」で応募してください。
Q05-04.
科学部で実施中の研究テーマとは異なる研究テーマで「B:自己推薦・自主研究推進型」にエントリーできますか?
A05-04.
高校の科学部などに所属している場合(高校の部活や学科単位で科学に関する活動を行っている場合)でも、そこで実施中の研究テーマと異なる研究テーマであれば「B:自己推薦・自主研究推進型」にエントリーできます。
Q05-05.
科学部で実施中の研究テーマと同じ研究テーマで「B:自己推薦・自主研究推進型」にエントリーできますか?
A05-05.
高校の科学部などに所属している場合(高校の部活や学科単位で科学に関する活動を行っている)場合で、かつ、そこで実施中の研究テーマを続けたい場合は、「C:学校推薦・連携活動型」にエントリーしてください。
Q05-06.
「C:学校推薦・連携活動型」の応募について、1グループの人数制限はありますか?
A05-06.
「C:学校推薦・連携活動型」は「1チーム3人まで」です。
研究指導の段階で、あまり多くの高校生を1つの研究室が受け入れることができません。また全国から多様な資質を持つ高校生を募り、受講機会を広げるためにもご理解ください。
Q05-07.
科学クラブの顧問をしています。クラブの生徒たちを「C:学校推薦・連携活動型」でFSSに応募させようと考えています。生徒5人で研究しているテーマがありますが、5人を2チームに分ける必要がありますか?
A05-07.
「C:学校推薦・連携活動型」は「1チーム3人まで」です。
該当生徒の意欲を確かめてください。FSSの第1段階では、講義やワークショップが月1,2回の頻度で行われ、毎回レポートや課題が課されます。このような活動を、学校生活と両立させながら継続して行う意欲が必要です。
チームでFSSの活動を行う場合、チーム内に意欲の差が見られ、意欲のある生徒に依存するケースもあります。
また、全国から多様な資質を持つ高校生を募り、受講機会を広げるためにもご理解ください。
Q05-08.
「C:学校推薦・連携活動型」で応募する場合、「志願書」と「調査書」はチームで1通提出すれば良いですか?
A05-08.
応募書類は、1人につき1通ずつご準備ください。
「志願書」の記述内容がチーム内で全く同じケースでは、FSSの活動への理解や参加への意欲が反映されているとみなすことができません。
「調査書」も、各応募者の特徴、資質、研究上の役割を個別に捉えたものにしてください。
Q05-09.
「C:学校推薦・連携活動型」で応募した場合、チーム内のメンバーは全て入校が許可されますか?
A05-09.
チーム内の全てのメンバーに入校を許可する保証はありません。
提出書類から個々の意欲を読み取り、個別に入校の可否を判断します。
これは、第1段階から第2段階に進む2次選抜でも同様です。
Q05-10.
「A:自己推薦・⼀般型」と「B:自己推薦・自主研究推進型」あるいは「A:自己推薦・⼀般型」と「C:学校推薦・連携活動型」あるいは「B:自己推薦・自主研究推進型」と「C:学校推薦・連携活動型」など、複数のエントリー形式で同時にエントリー(併願応募)できますか?
A05-10.
応募者1人につき、1応募形式で申請してください。
現在応募者が多数となり、1次選抜の段階で入校を認められない高校生がいます。全国から多様な資質を持つ高校生を募り、受講機会を広げるためにも、重複応募はご遠慮ください。
Q05-11.
「B:自己推薦・自主研究推進型」で応募したいと思っていますが、何かしらの科学賞を受賞していなければ「B:自己推薦・自主研究推進型」では応募できないのでしょうか?
A05-11.
「B:自己推薦・自主研究推進型」は、既に自分のテーマをもって研究をしている方を対象としていますが、科学賞の受賞実績がなくても応募できます。科学賞実績がない場合は、「小論文(別紙様式2)」の「これまでの研究業績(科学賞受賞等,400字以内)」に、これまで取り組んできた研究で科学賞やコンテストに応募した経験、報告書やレポートを書いた経験、課題発表や研究発表をした経験などを記して提出ください。
<受講準備>
Q06-01.
受講するために必要な準備がありますか?
A06-01.
ワークショップや研究発表の準備でノートパソコンが必要になります。
なるべく、WindowsパソコンまたはMacパソコンを用意してください。
Q06-02.
パソコンはどのようなときに使いますか?
A06-02.
①研究発表の資料づくり、ワークショップでのプレゼン資料作りに使います。
②毎回の講義後のレポート提出、研究指導の報告はオンラインで行います。
③リモート環境でグループワークや研究相談を行います。このとき、Zoom、Google (classroom) などを使います。
④講座のスケジュール連絡や出欠の報告、レポート課題の指示などをメールで行います。
⑤一部リモートで実施する講義では、動画の視聴を行います。
Q06-03.
実験などで白衣やゴーグルの準備は必要ですか?
A06-03.
受講生自身が準備する必要はありません。
研究指導の担当教員の指示で、安全のため、白衣やゴーグルが必要になった場合はFSSの予算で購入します。実験によってはラテックス製の手袋などを着用する場合がありますが、それもFSSの予算で購入します。
Q06-04.
FSSに入校後、連絡はどのようにして⾏いますか?
A06-04.
基本的にメールのみで連絡を⾏います。
応募するときに、自分自身のメールアドレスを取得しておいてください。また、メールの使い方に慣れておいてください。
受講生とFSS事務局が連絡用に用いるメールアドレスは入校手続きの際にお伝えします。
<経費・保険>
Q07-01.
受講するのに、費用はかかりますか?
A07-01.
受講料は無料です。
来学のための交通費を⼀部支援しますが、立替が必要になります。大学内の手続きの関係で、交通費の振込まで数か月がかかります。
なお、昼食等の飲食代は自費で支出してください。
Q07-02.
研究にかかる経費は、自分が支出するのですか?
A07-02.
本事業は国の予算で行います。「研究力養成コース」「研究力発展コース」では、研究指導の担当教員を通して必要な器具や消耗品類を購入します。研究指導の担当教員に伝えた予算内で研究を行うようにお願いしています。大学の規定で支出できない品目や購入方法に関しては、受講生が負担する可能性があります。
Q07-03.
保護者が車で送迎することは可能ですか?
A07-03.
基本的には、公共交通機関での来校をお願いしています。怪我等で公共交通機関の利用が困難な場合は、FSS事務局にご相談ください。
Q07-04.
受講中にケガをしたらどうなりますか?
A07-04.
実験中・作業中の事故などには、こちらも十分注意し、安全第一としています。また、実験そのものに危険が生じないよう、指導教員やティーチングアシスタント(TA)の指示に従ってください。
万一、ケガや体調不良が発生した場合は、救急車の手配や最寄りの救急病院での治療措置をします。
Q07-05.
保険の加入は必要ですか?
A07-05.
事務局では、FSSの経費で、受講生一律に損害保険への加入手続きを行います。この保険では、活動中の怪我や活動場所への移動中の交通事故による怪我の治療に対する補償が行われます。また、研究室の実験設備に損害を与えた時も、補償の対象となります。
<講座の受講と修了>
Q08-01.
「基礎力養成コース」から「研究力養成コース」「研究力発展コース」には、どのように進んだら良いですか?
A08-01.
第1段階を「基礎力養成コース」、第2段階を「研究力養成コース」、第3段階を「研究力発展コース」と言います。入校後の各段階で、出席状況、課題レポートの提出状況、研究への取り組み状況を評価して、修了を認定します。修了が認定された受講生(認定される見込みの受講生)の内、所定の審査を経て選抜された人が、次の段階に進めます。
Q08-02.
欠席の連絡はどうしたらよいですか?
A08-02.
入校決定後、皆さんとFSS事務局の連絡用にメールアドレスをお伝えします。
事前に、このアドレスを使ってメールで連絡をしてください。
Q08-03.
病気や学校行事などで欠席した場合はどうなりますか?
A08-03.
欠席した場合も、連絡用メールを使って授業資料を提供します。事務局よりメールで指示された方法で自習を行い、レポートを提出してもらいます。
この場合は出席扱いにはなりません。欠席が多い場合は各段階の修了を認定しません。
また、レポートの未提出が多い場合も、各段階の修了を認めません。
Q08-04.
「研究力養成コース」「研究力発展コース」でも講義がありますか?
A08-04.
「研究力養成コース」「研究力発展コース」でも、月1回程度、対面でワークショップを行います。日程は、基礎力養成コース開講後お伝えします。
Q08-05.
「研究力養成コース」「研究力発展コース」で行う研究の日程や場所は決まっていますか?
A08-05.
研究に関する個別指導の日程、方法、場所は指導担当教員と受講生の間で相談して決めます。
<研究テーマ>
Q09-01.
研究力養成コースでは、どんな研究をやっていますか?
A09-01.
2024年6月16日(日) 研究力養成コース研究発表会の活動報告を、次のURLより確認してください。研究発表会の様子と発表された研究のタイトルが紹介されています。
https://fss.shizuoka.ac.jp/240616kenkyuhappyoukai/
Q09-02.
研究テーマをどのように決めたらよいですか?
A09-02.
入校後、「基礎力養成コース」のメインレクチャーで、大学で行う学問の姿を学んでください。さらに、研究提案書の書き方など、研究への向き合い方に関する基本的な講義を行います。
「研究力養成コース」以降では、主体的に研究活動ができる人を求めています。研究テーマを受講⽣が自分自身で考え、計画を立て、研究指導者に働きかける必要があります。
そのために、普段から科学や科学技術に関する話題に目を向けたり、学校の理科の授業でいろいろな疑問を持ったりすることが重要です。
Q09-03.
私は動物が好きで、小さい頃から動物を飼ってきました。動物の研究者になるのが夢で、FSSに⼊って動物の行動の研究をしたいです。
A09-03.
実験動物を扱うためには、静岡大学動物実験規則(https://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000063.htm)に則した手続きが必要になります。指導担当予定教員と受講生の間で動物実験の実施可能性や実験計画を相談してください。
参照:実験動物委員会(https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/animal/)
Q09-04.
心理学、言語学あるいは経済学のような、人文系・社会科学系のテーマをやってみたいのですが、応募できますか
A09-04.
応募できます。
科学研究には、様々な研究対象や手法があります。未来の科学者養成スクールが提供する環境において実施可能なテーマかどうかは、2次選抜(研究力養成コース受講のための選考)への応募で提出する「研究提案書」をもとに検討します。
なお、人を対象とする研究には、静岡大学における人を対象とする研究に関する規則(https://reiki.adb.shizuoka.ac.jp/act/frame/frame110000598.htm)に則した⼿続きが必要になります。指導担当予定教員と受講生の間で実施可能性や実験計画を相談してください。
参照:人を対象とする研究倫理委員会(https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/homo/)
<その他>
Q10-01.
FSSへの応募方法について、静岡大学FSS事務局へ連絡してもよいですか?
A10-01.
入校前の静岡大学FSS事務局への連絡は、なるべくお問合せフォームを利用ください。
Q10-02.
入校が許可された後、FSS事務局との連絡はどうしたらよいですか?
A10-02.
入校手続きの連絡の際、FSS事務局との連絡用に使うメールアドレスをお伝えします。以降、そのメールアドレス宛に問い合わせや連絡をお願いします。
静岡大学FSS事務局へメールで連絡する場合は、以下のようなメールマナーを守ってください。
①メール件名に「FSS」「受講生番号」「用件が分かる見出し」を必ず書く。
②メール本文中に「受講生番号」「氏名」「連絡先(メールアドレス・電話番号など)」を明記する。
Q10-03.
問い合わせへの回答は、どのような方法でいただけますか?
A10-03.
送信されたメールのアドレスあるいは入校時登録したメールアドレスに回答します。
このとき、次の2点を注意してください。
①携帯端末でメールの送受信をする場合、端末のメールアプリが、パソコンからのメールに対し受信拒否に設定されていないことを確認してください。
②受信したメールが「迷惑メールフォルダ」に自動的に振り分けられている場合があります。「受信フォルダ」に該当メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。
![静岡大学[FSS]未来の科学者養成スクール](https://fss.shizuoka.ac.jp/wp-content/uploads/2017/06/edd37c1d5bf1135b06e65144ae37a341.gif)